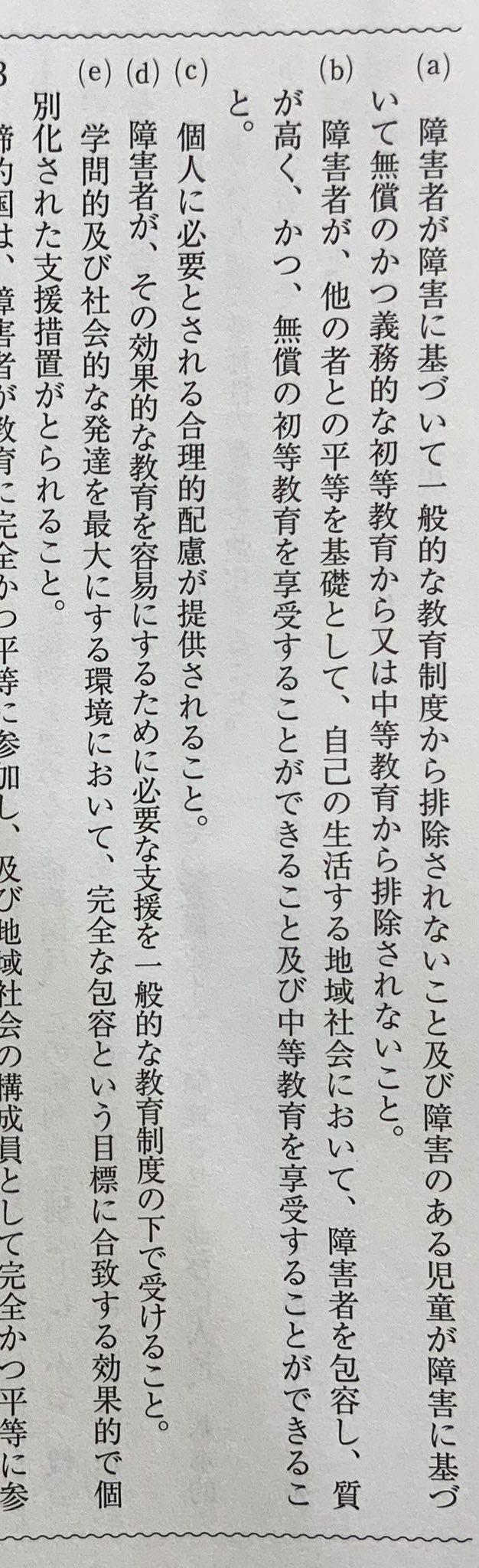中央区議会第三回定例会本会議での、区政の議論2025.9.18 3人の議員からの一般質問への答弁を整理します。
<企画総務費>
●情報化基本方針
・区長は、令和8年度末までにオンライン化で対応できる手続きについて100%達成を目指す。
・区長は、高齢者向けのスマートフォン教室やサイバー犯罪防止のための防犯教室を継続して実施する。
●施設管理
・区長は子ども・子育て関連施設やクーリングシェルターにサーバー型の給水器を設置するなど熱中症予防を強化する。
●多文化共生
・区長は、多文化共生の重要性を人権週間における啓発など、あらゆる機会を通じて発信していく。
・区長は、外国人住民の生活実態の基本的な調査を実施していると述べ、今後もサービス向上に努める。
●ワークライフバランス
・区長は男性職員の育休取得率の目標(令和11年度までに育休取得期間2週間以上の取得率85%)達成に向けた取り組みを進める。
・区長は父親が参加しやすい時間帯での講座開催やオンラインを活用した既存事業の見直しなど、父親同士が交流活動できる機会を充実させる。
・区長はワークライフバランス推進企業認定事業のアドバイザー派遣を中心に、事業所の自主的な取り組みを後押しし、誰もが働きやすい職場づくりを推進する。
●防災
・区長は、総合防災システムの構築を進め、年明けから全庁を挙げてテスト運用を開始する。
・区長は、備蓄物資の一元管理に着手し、DX活用による在庫管理を図る。
<区民費>
●共通買物券
・区長は、区内共通買い物食事券の電子化に向けて、共通アプリでの運用を想定した検討を加速させる。
●デジタル地域通貨
・区長は、ポイント付きデジタル地域通貨の導入について、他自治体の事例を参考にしながら慎重に検討する。
<福祉保健費>
●子育て支援
総論
・区長は中央区らしい子ども真ん中のまちづくりを進めていく。
・区長は子育て支援の満足度を向上させる取り組みを行う。
妊娠期
・区長は、搾乳に関する意識啓発をホームページや広報誌等で進め、公共施設でのスペース確保と分かりやすい表示について検討する。
乳児期
・区長は、産後ドゥーラを産後支援の選択肢として妊婦面談で紹介するなど、母親が適切な支援を受けられるよう努める。
児童、青年期
・区長は、ヤングケアラー支援のため、関係機関との連携強化や情報共有の場を充実させる。
●高齢者福祉
・区長は、高齢者の生活実態調査において終活へのニーズを確認し、本人の意思に即した終末期を迎えられる取り組みを進める。
・区長は、福祉用具の展示内容や相談体制の充実を図る。
・区長は、高齢者の熱中症対策として、意識啓発や予防策の実践を継続する。
・区長は、介護保険制度について、高齢者とその家族が安心してサービスを利用し続けられる制度となるよう、区長会等を通じて国に要望していく。
・区長は、シルバーパスに関する東京都の取り組みについて、区のお知らせやチラシの配布などによる周知を図る。
<環境土木費>
●緑化
・区長は、令和10年度に改定予定の中央区緑の基本計画の事前調査でヒートアイランド現象の緩和に資する調査項目を追加し、効果的な公園等のクールスポットについて検討する。
●公園
・区長は、令和8年度までにすべての公園・児童遊園に防犯カメラの設置を完了させる。
区長は、地域の要望を踏まえ、かまどベンチ等の防災資機材の整備を進める。
・区長はカルバートの広々とした空間を活用した子どもの遊べる場の検討を進める。
・区長は既存公共施設のスペースを有効活用した遊び場の提供を検討する。
<都市整備費>
●市街地再開発事業
・区長は、市街地再開発事業の見直しにあたり、従前権利者への影響に配慮するよう再開発組合に対して指導を継続する。
●耐震化
・区長は、新耐震基準の建築物に対する助成制度の新設や既存の助成制度の拡充を検討していく。
以上